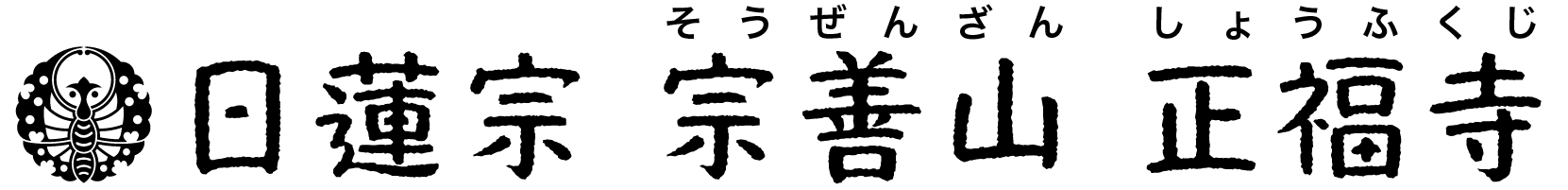「ノアの方舟」と「三車火宅の喩え」
昨晩のNHKで作家の荒俣宏氏が宗教学者の山折哲雄氏との対談が放映されていました。
たまたまテレビを付けたところで、山折氏から「法華経」「譬喩品」などという言葉がでたのでオッと思いました。(対談の最後しか見れなかったが残念でしたが…)
対談で山折氏は、日本が戦後享受してきた資本主義、物質主義、競争社会というものは、実は西洋の旧約聖書にある「ノアの方舟」にみる犠牲が伴う選民主義的思想から来ていると指摘されていました。
いっぽう東洋の思想を代表する仏教「法華経」にある「三車火宅のたとえ」こそ、元来東洋、日本の思想の根底をなすと指摘されました。
その「三車火宅のたとえ」とは、法華経の中で説かれる七つの喩え話しの一つで、私たち日蓮宗ではとても馴染みが深い教えです。
簡単にあらすじをいいます。ある時、長者の大邸宅が火事となり、火事に気付かず遊び戯れる子供たちを、長者が門に3種類の乗り物を用意し燃えさかる炎の中から子供たちを救い出したという話です。実はここで言う長者は仏、子供は凡夫である私たち衆生を指します。つまり仏の分け隔てのないすべての者への救いが説かれています。
東日本大震災を受けエネルギー問題、環境問題など戦後定着したあらゆる価値観について今、大きな転換期であることは誰もが感じているところだと思います。
現代に「三車火宅の喩え」を読むことの重要性を考えさせられました。